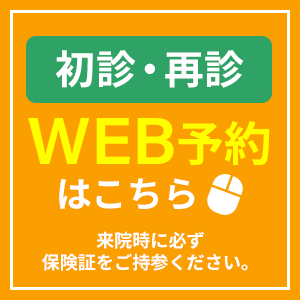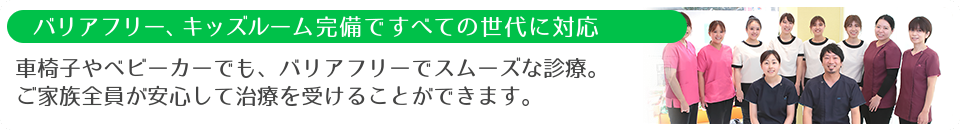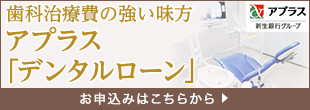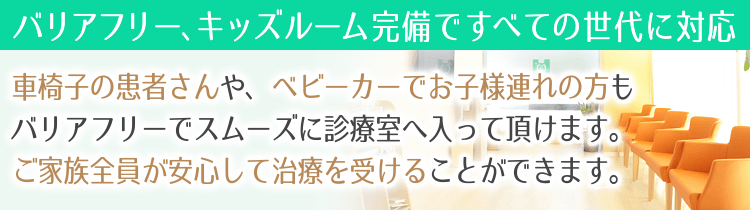こんにちは。
大阪府吹田市江坂の「はやし歯科クリニック」です。
今回は妊娠中の歯科ケアについてお話しします。
妊娠中は身体の変化に伴い、お口の中にも変化が起きます。
妊娠時に起きやすいお口の中の変化、歯科治療について、赤ちゃんの歯の発育について解説します。
妊娠時に起きやすいお口の中の変化

①妊娠性歯肉炎
妊娠中には、ホルモンの変化が起き、その影響で歯ぐきが腫れ、出血しやすくなります。
妊娠性歯肉炎は、特に歯ぐきの炎症が起こりやすく歯みがきの時に出血しやすいですが、普通の歯肉炎と症状は変わりません。
放置して歯肉炎が悪化すると、早産や低体重児のリスクが高まります。
日頃の丁寧な歯みがきが、妊娠性歯肉炎の予防につながります。
一度、歯科医院で相談し、プラークコントロールや歯石の除去など適切な治療を受けましょう。
②むし歯になりやすい
つわりにより、歯みがきが充分にできなかったり、食事の回数が増えたり、お口の中の環境が悪化してむし歯のリスクが高まります。
⓷唾液分泌が少なくなる
妊娠中、ホルモンの変化で、唾液の分泌が減少することがあります。
口の中が乾燥して唾液がネバネバし、自浄作用が低下します。
そのため細菌が繁殖し、むし歯や口臭の原因となります。
④親知らずが腫れる
妊娠中、ホルモンの影響やお口の中の状態の変化が関連して、親知らずが腫れたり、痛みを引き起こすことがあります。
妊娠時期別に対策

妊娠時に起きやすいお口の中の変化に対して、妊娠時期別に対策をお伝えします。
初期(0~3ヶ月)
個人差がありますが、つわりで歯みがきがつらいときは、洗口液などを利用してブクブクうがいをしましょう。
ヘッドの小さい歯ブラシを使用して、歯ブラシは小刻みに動かし、夜寝る前はお口の中を清潔にしてください。
歯磨きの際は、下の方を向いて前かがみの体勢にし、、歯ブラシを舌に当てないようにすると嘔吐感を避けやすいです。
食の嗜好も変わりやすく、糖分の多い飲食物や酸性食品をだらだら食べることは控えましょう。
中期(4~7ヶ月)
お腹が大きくなるにつれ、胃が圧迫され一度に食べられる量が減ってしまうため、空腹状態が多くなり、間食などの「食べる回数」が増えやすい時期です。
妊娠中は唾液の量が減り、自浄作用が低くなるため、食後の歯磨きによるケアが重要です。
お口の中の環境を良くして、むし歯や歯周病のリスクを減らしましょう。
妊娠中はむし歯や歯周病になりやすく、むし歯や歯周病の初期症状に気づきにくいものです。
つわりがおさまる4〜5ヶ月頃に歯科健診を受けて、比較的体調の安定した妊娠中期に必要な歯科治療を済ませておくのがよいでしょう。
歯科治療に当たっては母子健康手帳を提示して、産婦人科医から注意を受けていることは必ず歯科医師に伝えてください。
もし、体調や気分が悪くなった時は遠慮なく申し出ましょう。
妊娠中はいつも以上に歯科治療に関して心配なことがあると思われますので、以下にお伝えします。
エックス線撮影の胎児への影響について
歯科治療で通常用いられるエックス線の放射線量はごくわずかです。
照射部位も子宮から離れているので、お腹の赤ちゃんにはほとんど影響はないといわれています。
ただし、妊娠していることを伝えて防護用エプロンを着用する必要がありますので、必ず妊娠していることをお伝えください。
歯科治療時の麻酔の使用について
通常の歯科治療に用いられる麻酔は局所麻酔で、使用量もわずかです。
局所で分解されるため、胎児には影響ありません。
痛みを我慢しての治療は、母体にも胎児にもストレスになるため、安定期には適切に使用した方がよいでしょう。
以前に歯科麻酔薬で気分が悪くなったことや、効きが悪く多量に使ったなどの経験がある場合は、よく歯医者さんと相談する必要があります。
薬の服用
妊娠初期はできれば薬の服用を避けたいものですが、中期以降の歯科治療で処方される薬剤は、妊娠中でも安全に使用できる薬剤が選ばれています。
不安、心配がある場合は、歯科医師や薬剤師や産科の主治医に相談しましょう。
後期に入ってお腹が大きくなるとあお向けで治療を受けるのが大変です。
何かお悩みがある場合は、妊娠中期(4〜7ヶ月)に当歯科医院に相談してください。
後期(8~10ヶ月)
生まれたあとの準備や日々の仕事や家事で忙しくなり、つい歯磨きをおろそかにしてしまいがちな時期です。
お母さんのお口の中が不健康だと赤ちゃんにも細菌をうつしてしまうリスクがあります。
産後は忙しくなるので、妊娠中に歯科医院へ行って、治療することをおすすめします。
ブラッシングだけでは取りにくいプラークには、歯科医院でのクリーニングや、フロスなどでキレイにしましょう。
妊娠中の食事に気をつけましょう

妊娠すると内分泌の変化やビタミン代謝の障害などにより、栄養障害が起きやすくなります。
それによってお口の中に障害が発生したり、胎児の歯の形成にも影響を及ぼす可能性があるので、妊娠中は特にバランスのよい食事を心がけましょう。
乳歯の元となる歯胚(しはい)と呼ばれる組織は、妊娠9週ころから作られます。
歯胚が石灰化されて、固く丈夫になってくるのが妊娠4ヶ月目ごろです。
永久歯の歯胚も、妊娠4ヶ月ころに作り始められます。
カルシウムだけでなく野菜やくだもの、魚、肉、穀物などをバランスよく食べて必要な栄養素をしっかり摂るよう心がけてください。
主な栄養素と働き
タンパク質 : 歯の基質を作る
カルシウム・リン : 歯の再石灰化に必要
ビタミンA :エナメル質に必要
ビタミンC : 象牙質に必要
ビタミンD : カルシウムの代謝や石灰化を調整する役割
歯周病と早産の関連性
歯周病の妊婦さんは歯周病でない妊婦さんに比べて約5倍も早産になりやすいです。
歯周病は、歯を支えている歯ぐき(歯肉)や歯槽骨(しそうこつ)を破壊する炎症性の病気で、全身のいろいろな病気との関連が明らかになってきています。
妊娠中は、女性ホルモンの増加により炎症に対する反応が増し、口の中で歯周病の原因菌が多くなります。
歯周病になると、体内の自分を守ろうとする細胞から、出産のサインになる物質が過剰に作られます。
さらに、子宮収縮を促進させる物質も作られ、早産につながることがあります。
早く生まれた赤ちゃんは、からだの機能が未熟なので生まれてからさまざまなことに注意が必要になります。
妊娠前からの歯周病の予防や治療は元気な赤ちゃんのためにも大切です。
赤ちゃんが生まれたあとのお口に関する注意

生まれたばかりの赤ちゃんの口には、むし歯の原因となる細菌(ミュータンス菌)はいません。
個人差はありますが、乳歯は生後5~8ヶ月頃から生えはじめると言われています。
歯は、唾液中のカルシウムなどを吸収して、時間をかけて強い歯になります。
赤ちゃんの生えたばかりの歯はとてもやわらかく、むし歯菌(ミュータンス菌など)がつくる酸にとても弱い状態です。
そのため、生えたての歯は穴があきやすく、むし歯の進行がとても早くなります。
離乳食が始まる生後5カ月ころから、特に注意が必要です。
食べた後はガーゼでやさしく拭いてあげてください。
また、前歯が生えてきたら歯ブラシで磨く習慣をつけましょう。
座った状態や立ったままだと頭が急に動いて、歯ブラシでお口の中を傷つける可能性があります。
歯みがきをするときは、お母さんが座って足の間に、お子さんを寝かせた状態で頭をしっかり固定してください。
上唇の裏側にある筋(上唇小帯)に当たると痛いので、前歯を左右にわけて縦磨きをしましょう。
イオン飲料や乳酸飲料は糖分が多く入っているので、脱水症状があるとき以外はジュースと同じだと考えてください。
お父さんやお母さんが使ったスプーンで赤ちゃんに食べさせたり、噛み砕いたごはんをあげたり、またキスしたりすることによって、実は赤ちゃんにむし歯菌をうつしてしまうこともあります。
ご家族みんなで気を付けましょう。
赤ちゃんとのスキンシップを取ることが多いお父さんやお母さんは、赤ちゃんのためにも、日頃からの歯磨きに気を付けてむし歯菌を減らしておき、健康なお口を維持してください。
まとめ

妊娠中は、つわりにより歯磨きがしにくくなり、これに伴い、むし歯の発生が心配されます。
また、妊娠中にむし歯になってしまうと、治療に関して妊娠前以上に適切な対応が必要となります。
ホルモンの変化により、歯肉炎や歯周病も進行しやすくなり、注意が必要です。
さらに、出産後も歯のケアは非常に重要です。
日頃から、お母さんだけでなく家族全員でオーラルケアを怠らないようにしましょう。
何かわからないことがあれば、当院へお問い合わせください。